こんにちは!YouTubeチャンネル「ギリギリ技術」のおきぺんです!
みなさん、毎日使う電気が、どこから来てどうやって届いているか、考えたことはありますか?
実は、発電所からみんなの家まで、電気は長い旅をしているんです。今回のテーマは「送電」。電気の大冒険の仕組みを一緒に見ていきましょう!今日の授業で、きっと電気のことがもっと好きになりますよ!
みんなの家まで電気はどうやって届くの?~主な道のり~
電気は発電所で生まれてから、いきなり皆さんの家へ来るわけではありません。いくつか「中継地点」を通って、少しずつ姿を変えながら届けられるんですよ。
- 発電所(はつでんしょ):電気を「生み出す」場所です。火力発電、原子力発電、水力発電など、いろんな方法で電気が作られます。
- 変電所(へんでんしょ):電気の「中継地点」です。発電所で作られた電気はまずここに運ばれて、家庭で使いやすいように電圧(電気の「高さ」)を調整したりします。
- みんなの家:変電所を経て、最終的に皆さんのコンセントまで電気が届けられます。
「送電」と「配電」って何が違うの?
電気の道のりには、呼び方が違う2つの区間があります。ちょっと紛らわしいので、しっかり区別して覚えましょうね!
- 送電(そうでん):発電所から変電所まで、電気を移すことを「送電」と言います。発電所から「送る」というイメージで覚えてください。
- 配電(はいでん):変電所からみんなの家まで、電気を届けることを「配電」と言います。「配る」というイメージですね。
「送電」と「配電」、似ている言葉ですが、それぞれ電気を運ぶ区間が違うので、間違えないようにしてくださいね!
電圧って何?電気の高さに注目!
電気には「電圧(でんあつ)」というものがあります。これは例えるなら、電気の「高さ」や「勢い」のようなものです。高すぎると危険だったり、低すぎると十分に家電が動かせなかったりします。
各地点での電圧の変化を見てみよう!
発電所で作られた電気は、段階的に電圧が下げられて、私たちの家庭で安全に使えるようになっているんです。これがとっても大事なポイントですよ。
- 発電所から変電所まで:ここでは、なんと30万ボルト(V)から50万ボルト(V)という、とてつもなく高い電圧で送られます。遠くまで効率よく電気を送るために、非常に高い電圧が必要なんです。
- 変電所からみんなの家まで(変圧器の前):変電所で一度電圧が調整され、私たちの近くまで運ばれるときには、6600Vという電圧になります。この後、さらに皆さんの家の近くにある「変圧器」という機械を通ります。
- みんなの家のコンセント:最終的に変圧器で調整された電気が家庭に届き、私たちが普段使っている家電に合うように100V(ボルト)の電源として供給されます。場合によっては200Vで使う家電もありますね。
このように、発電所から変電所、そして家庭へと進むにつれて、電圧はどんどん下がって、私たちが安全に使いやすい状態になって届けられているんですよ。
発電量ってどうやって決めてるの?~電気の予測と需要~
「電気って、必要な時に必要なだけ作ってるのかな?」と思ったことありませんか?実は、発電所では、電気の「使用量」を予想して発電しているんですよ。電気は貯めておくのが難しいので、使う量に合わせて作る必要があるんです。
電気を使う量が多い時期はいつ?
一年の中でも、特に電気をたくさん使う季節と、そうでない季節があります。みなさんも想像してみてくださいね!
- 冬:めちゃくちゃ寒いと、暖房をガンガン使いますよね!
- 夏:めちゃくちゃ暑いと、エアコンをフル稼働させますよね!
そうなんです!電気の使用量は、基本的に冬と夏が多く、春と秋は比較的少ない傾向にあります。だから、発電所では、こうした季節ごとの電気の使用量を予想して、発電量を調整しているんですよ。
まとめ
今日の授業では、発電所から私たちの家まで、電気がどのように届けられるか、その仕組みについて詳しく見てきました。ポイントを振り返ってみましょう。
- 電気は発電所で生まれ、変電所を中継して家庭に届けられること。
- 発電所から変電所への移動が「送電」、変電所から家庭への移動が「配電」であること。
- 電気が家庭に届くまでに、高い電圧から段階的に低い電圧へと調整されていること。
- 発電所では、電気の使用量を予測して発電量を調整していること。特に冬と夏は使用量が多いこと。
普段何気なく使っている電気にも、こんなに複雑で大切な仕組みがあるんですね。今日の学びが、皆さんの電気への興味を深めるきっかけになったら嬉しいです!
君ならできます。頑張って!
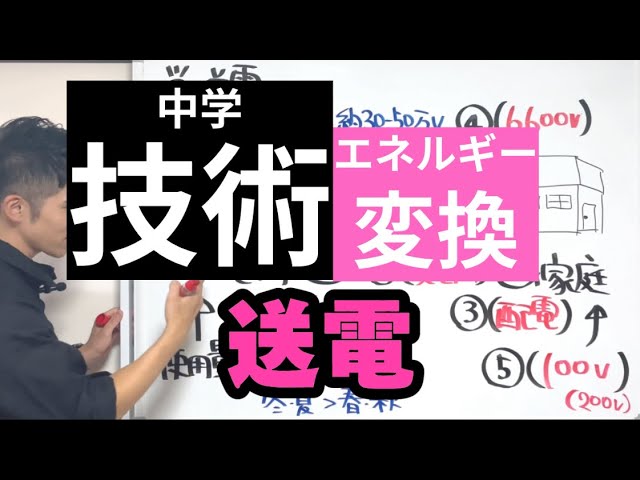


コメント