みなさん、こんにちは!元中学校技術科教員の「おきぺん」です。YouTubeチャンネル「ギリギリ技術」も運営しています。
今回は、みなさんの身近にある家電製品が、一体どういう仕組みで動いているのか、その「心臓部」ともいえる電気回路について、一緒に学んでいきましょう!今までエネルギーの話や、電気をどうやって送るか、という大きな話をしてきましたが、今回はもっと具体的な仕組みに注目していきますよ。普段何気なく使っているテレビや扇風機、その中にはどんな秘密が隠されているんでしょう?きっと「なるほど!」って思えるはずです。
電気回路って、一体なんだろう?
さて、早速ですが「電気回路」って聞くと、ちょっと難しそうに感じますか?
でも、実はとってもシンプルなんです。
簡単に言うと、電気回路とは、電気を流して何かを動かすための「道筋」のことなんです。具体的には、次の4つの要素から構成されていますよ。
- 電源(でんげん):電気を供給するところ。
- 導線(どうせん):電気を流す線。
- 負荷(ふか):電気を使って動くもの。
- スイッチ:電気のオンオフを切り替えるもの。
イメージしてみてください。みなさんの家にある家電製品、例えばテレビを思い浮かべてみてください。必ずコンセントにつながっていますよね?それが電源です。テレビの中にはたくさんの導線が張り巡らされています。そして、テレビの画面が光ったり、音が出たりしますよね。それが負荷です。最後に、テレビの主電源を入れたり消したりするボタン、それがスイッチの役割なんですよ。
電気回路を「正しく」表すルール
電気回路は、誰が見ても同じように理解できるように、ルールが決まっています。それが「電気用図記号(でんきようずきごう)」を使った「回路図(かいろず)」で表す、というものです。
この電気用図記号は、「JIS(ジス)」という日本の日本産業規格で定められた統一の記号なんです。だから、日本中の誰が見ても「これはモーターだ!」「これはランプだ!」とわかるようになっているんですよ。これは、設計図を書いたり、修理をしたりする時に、とっても大切なルールなんです。
電気回路を構成する要素を詳しく見てみよう!
では、先ほど説明した4つの要素を、もう少し詳しく見ていきましょう。
① 電源(でんげん):電気の出発点!
電源は、電気回路に電気を供給する「スタート地点」です。身近なものでは、懐中電灯に入れる乾電池や、お家の壁にあるコンセントから得られる家庭用電源が代表的ですね。
② 導線(どうせん):電気の道!
導線は、電気を運ぶ「道」のようなものです。銅などでできていて、電気をスムーズに流してくれます。回路図では線で表されますが、実際にはたくさんの細い線が束ねられていたりします。
③ 負荷(ふか):電気の働き者!
負荷は、電気を受け取って、ある「動き」や「動作」をするものです。簡単に言うと、エネルギーを別の形に変換する部分のことです。例えば、扇風機を動かすモーターや、光を出すLED、懐中電灯の豆電球などが負荷にあたりますね。
④ スイッチ:電気の司令塔!
スイッチは、電気の流れを「制御する」役割を持っています。つまり、電流を流したり、止めたりすることで、家電製品のオンとオフを切り替えることができるんですね。物によってはスイッチがないものもありますが、多くの家電製品には必ず組み込まれています。
回路図で見てみよう!実際の家電製品の仕組み
動画の右下にある図を覚えていますか?あれこそが、私たちが学ぶ回路図です。
あの回路図には、スイッチ、電源、そして2つの負荷(モーターとランプ、つまり豆電球ですね!)が描かれています。この図は、電気が2つの道に分かれて流れる「並列回路(へいれつかいろ)」という形になっています。
この回路図のスイッチをオンにすると、どうなると思いますか?そう、電気が電源から導線を伝って流れ出し、並列に分かれた道を通って、モーターもランプも両方ともオンになる仕組みになっているんです。
このように、一般的な家電製品は、電源、導線、負荷、スイッチという要素がしっかりつながって、初めて動くようになっているんですよ。
まとめ
今回は、身近な家電製品の「中身」、つまり電気回路について学んできましたね。
電気回路は、電源、導線、負荷、スイッチの4つの要素で構成されていること。
そして、それらをJISで定められた電気用図記号を使って、回路図として正しく表すルールがあることを学びました。
この電気回路の知識は、中学の物理の授業でも出てくる大切な内容なので、ぜひ今のうちにしっかり理解しておいてくださいね。
君ならできます。頑張って!
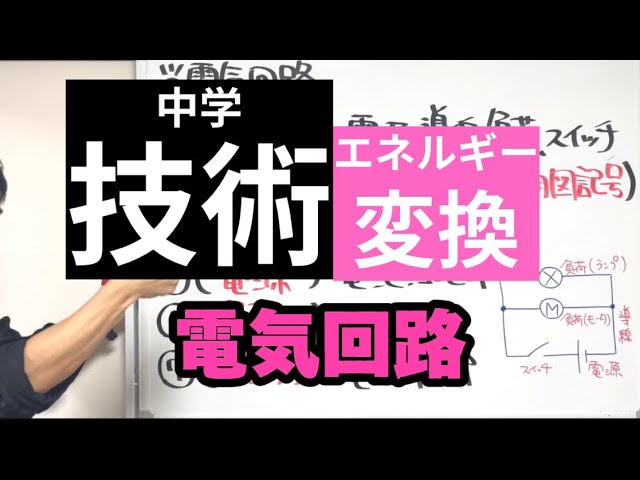


コメント