こんにちは!元中学校技術科教員のおきぺんです。
今回の記事では、中学校の技術科でとっても大切な「金属とプラスチックの加工」について、一緒に楽しく学んでいきましょう!前回の木材加工に続いて、今回はちょっぴり難しそうに感じるかもしれませんが、動画で見た内容をしっかり整理して、テストにもバッチリ対応できるように解説していきますね。「加工」って聞くと難しそう…と思うかもしれませんが、身の回りにある色々なものがどうやって作られているのかを知ると、もっと技術が楽しくなりますよ!
学習内容のポイント解説
金属の加工:薄い板を「曲げる」方法
まずは金属の加工から見ていきましょう。金属の薄い板を曲げるのって、どうやったらできると思いますか?実はいくつか方法があるんですよ!
- 折り曲げ機(おりまげき)
- これは、薄い金属板を曲げるためだけに作られた専用の機械です。曲げたい位置に線(けがき線)を合わせて、ガチャン!と機械が自動で曲げてくれるイメージですね。
- 当て木(あてぎ)を使う方法
- これは、台の上に当て木を置いて、クランプでしっかりと挟み、別の当て木を使って人の力でゆっくりと曲げていくアナログな方法です。教科書にも載っていることが多いので、絵と合わせて確認すると分かりやすいですよ。
- 折り台(おりだい)と打ち木(うちき)を使う方法
- 「折り台」という、角に金属がついた台に、曲げたい線(けがき線)を合わせます。そして、「打ち木」という木材を使って、ガンガンと叩きながら金属を曲げていく方法です。こちらも人の力を使う、昔ながらのやり方ですね。
教科書によって紹介されている内容が少し違うこともあるので、皆さんの教科書やノート、プリントの内容もしっかり復習しておくと良いですよ!
金属の加工:棒材を「曲げる」方法
薄い板に比べて、棒状の金属を曲げるのは少し難しいです。
- 棒の根元を万力(まんりき)という工具でしっかりと固定します。
- 棒にかぶせるような形のパイプを使って、グッと力を入れて曲げていきます。
専用の工具もありますが、この方法がテストには出やすいかもしれませんね。
金属の加工:ネジを作る「ネジ切り」
金属の加工では、「ネジ」を作る技術もとても大切です。ネジには2種類あるのを知っていましたか?
めねじ(メネジ)の作り方
「めねじ」とは、ネジを受け入れる側、つまりネジ穴のことを指します。
- 使う工具は「タップ」と「タップ回し」です。
- まず、金属に下穴を開けます。そこにタップをセットし、タップ回しを使ってゆっくりと回しながら、ネジの溝(ネジ山)を作っていきます。
- 作業中は、出てくる金属のカス(切粉)をしっかり取り除き、油を使いながら作業を進めることがポイントです。
おねじ(オネジ)の作り方
「おねじ」は、私たちが普段よく見る、ボルトのようなネジそのものを指します。
- 使う工具は「ダイス」と「ダイス回し」です。
- ダイスをダイス回しに固定し、金属の棒材にセットします。そして、これもゆっくりと回しながら、棒材の表面にネジ山を作っていきます。
これらの手順や使う道具の名前、しっかり覚えておいてくださいね!
プラスチックの加工:ヒーターで「曲げる」
さあ、最後にプラスチックの加工です!プラスチックって、そのまま力任せに曲げようとすると、パキッと割れてしまいますよね。そこで登場するのが、ある便利な道具です。
- 曲げ用ヒーター(まげようヒーター)
- これは、プラスチックを曲げたい部分だけを温めて、柔らかくするための専用ヒーターです。
- ヒーターの赤い部分で、曲げたいプラスチックの場所をじっくりと加熱します。柔らかくなったら、台の角などを利用してゆっくりと曲げ、形が決まったら濡れた布などで冷やし固めます。
ここで重要なポイント!プラスチックには「熱可塑性(ねつかそせい)」と「熱硬化性(ねつこうかせい)」という種類があることを学習しましたよね。このヒーターで曲げられるのは、熱を加えると柔らかくなって形を変えられる「熱可塑性プラスチック」だけなんです。もし、熱を加えても柔らかくならない「熱硬化性プラスチック」を無理に曲げようとすると、やっぱり割れてしまうので注意してくださいね!
まとめ
今回は、金属とプラスチックの加工について学びました。
- 金属の薄板の曲げ方には、折り曲げ機、当て木、折り台と打ち木を使う方法がありましたね。
- 棒材は、万力とパイプを使って曲げるんでした。
- ネジ作りでは、めねじを作る「タップとタップ回し」、おねじを作る「ダイスとダイス回し」が重要でした。
- プラスチックは、曲げ用ヒーターで熱して柔らかくしてから曲げ、冷やし固めるのがポイントでした。そして、これが熱可塑性プラスチックの特性と結びついていることも理解できました。
それぞれの道具の名前や使い方、そして材料の性質をしっかり理解できたでしょうか?
テストでこの内容が出るときは、教科書やワークの問題を解いて、手順やポイントをしっかり復習してくださいね!
君ならできます。頑張って!
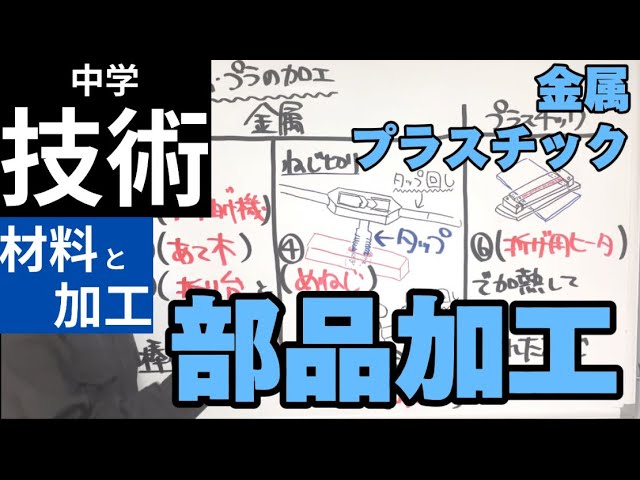


コメント