はい、みなさんこんにちは!元中学校技術科教員のおきぺんです。
今回のテーマは、私たちの身の回りにある「機械」の動きのひみつです!YouTubeチャンネル「ギリギリ技術」の授業動画の内容を、もっとわかりやすく整理して、機械がどんなふうに動いているのか、その「運動の種類」について一緒に楽しく学んでいきましょう。難しい話は抜きにして、優しく解説していきますので安心してくださいね!
機械が「仕事」をするってどういうこと?
「機械は外からエネルギーが加わって仕事をする」…授業動画でこの言葉を聞きましたよね。私たちが普段使う「お仕事」とは、少し意味が違うんですよ。
理科で学ぶ「仕事」の概念
技術科でいう仕事とは、「外から力が加わって、それが移動する、つまり動くこと」なんです。中学3年生の理科(物理)でも詳しく学びますね。
機械の基本的な役割は、「人間が使いやすいように、目的に合わせて力が加わって動く」こと、つまり「仕事をする」ことなんですよ。機械は私たちの代わりに、色々な「仕事」をしてくれている、というわけですね!
機械の動きを支える3つの「ブロック」!
この機械が「仕事」をするには、大きく分けて3つの部分(ブロック)が連携して動いています。それぞれに大切な役割があるので、一つずつ見ていきましょう!
1.原動機(げんどうき)
最初のブロックは「原動機」です。ここは、熱エネルギーや電気エネルギーを、実際に機械を動かすための運動エネルギーに変換する部分なんです。例えば、ハンドミキサーのモーターを想像してみてください。コンセントからの電気を「回る力」に変えてくれる部分、それが「原動機」です!
2.伝動機(でんどうき)
次に紹介するのは「伝動機」です。原動機で生まれた「動く力(動力)」を、次の「作業機」へと伝える役割をします。ハンドミキサーでは、モーターから泡立てる部分に力を伝える歯車などがこれにあたります。動きの方向を変えたり、速さを変えたりするのも、この伝動機の役割なんですよ!
3.作業機(さぎょうき)
そして最後のブロックが「作業機」です。ここは、機械が実際に目的とする作業を行う部分、つまり「一番動いてほしいところ」なんです。ハンドミキサーでいうと、メレンゲを泡立てるためにぐるぐる回る、あの泡立て器の部分が「作業機」ですね。ここが機械の「一番の目的」となる動きをしてくれるんです!
このように、私たちの身の回りにあるほとんどの機械は、「原動機」→「伝動機」→「作業機」という順番で力が伝わり、動いているんですよ!
こんなにある!機械の「運動の種類」3つ!
さて、機械が動くとき、その動き方にもいくつかの種類があるんです。大きく分けて3つありますので、遊園地のアトラクションを例に見ていきましょう!
1.直線運動(ちょくせんうんどう)
「直線運動」とは、その名の通りまっすぐな線に沿って動く運動のことです。例えば、遊園地のメリーゴーランドの馬を思い浮かべてください。馬が上下に動く、このまっすぐな動きが「直線運動」なんですね!
2.回転運動(かいてんうんどう)
次に「回転運動」です。これは、ある点を中心に、ぐるぐると回り続ける運動のこと。きれいな円を描いて、周期的に(繰り返して)回るのが特徴です。遊園地のコーヒーカップのアトラクションは、この回転運動の代表例ですね!
3.揺動運動(ようどううんどう)
そして最後が「揺動運動」です。これは、ある場所を軸にして、ゆらゆらと揺れ動くような動きのこと。直線でも回転でもない、独特の動きなんですよ。一番わかりやすいのは、車のワイパーの動きです。ある点を軸にゆらゆらと揺れ動く、これが「揺動運動」なんですよ!
身の回りには、この3つの運動が組み合わさって動いている機械もたくさんあります。ぜひ探してみてくださいね!
まとめ
今回は、機械が動く基本的な仕組みと、その「運動の種類」について学びました。機械は「仕事」をするために、「原動機」「伝動機」「作業機」という3つの部分に分かれて動いていること、そして、その動きには「直線運動」「回転運動」「揺動運動」の3つの種類があることが分かりましたね。
この知識があれば、これから身の回りの機械がどう動いているのか、もっと深く理解できるようになるはずです。ぜひ、今日学んだことを思い出して、普段の生活の中で観察してみてくださいね!
君ならできます。頑張って!
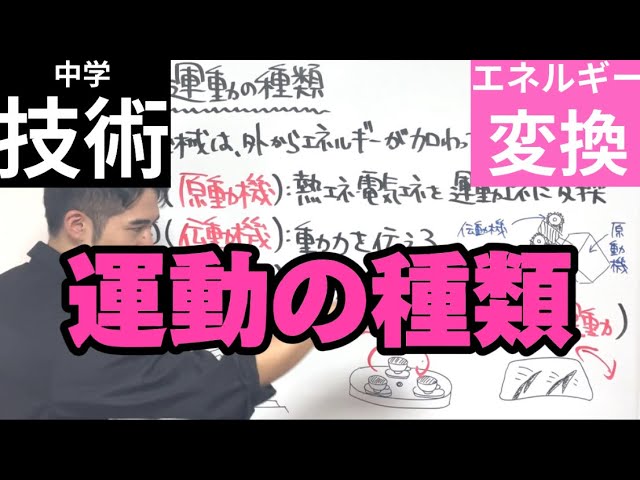



コメント