皆さん、こんにちは!「ギリギリ技術」のおきぺんです。元中学校技術科教員として、皆さんの技術の授業がもっと楽しく、もっと深く理解できるようにお手伝いしたいと思っています!
さて、皆さんはこれまでに、材料の特徴や丈夫な構造について学んできましたよね。でも、いざ「こんな棚を作ってみたい!」と思ったとき、頭の中のイメージをどうやって形にしたらいいのか、迷うことはありませんか? 今回からガラッとテーマを変えて、「製図(せいず)」について一緒に学んでいきましょう!製図は、皆さんが実習で素敵な作品を作るための「設計図」を書く、とっても大切な作業なんですよ。どんな種類の図があって、それぞれどんな時に役立つのか、一緒に見ていきましょうね!
製図の全体像を掴もう!
製図の世界は奥が深いですが、まずは全体像を掴むことが大切です。今回から5、6回にわたって製図についてじっくり解説していきますので、一緒に頑張りましょう!
① 構想図(こうそうず)ってどんな図?
まず最初に紹介するのは「構想図」です。これは、皆さんの頭の中で生まれた「こんなものがあったらいいな」というアイデアを、最初に絵にしたものなんです。例えば、「机の上が本で散らばっているな、本を置ける棚があったら便利なのにな」という悩みから、「コンパクトで、文庫本や小説がしっかり奥まで入る棚があったらいいな」とイメージしますよね? そのイメージをパッと書き出したものが、この構想図なんです。書き方に特別なルールはないので、自由に描いてみてくださいね!
製図のルール「JIS(ジス)」とは?
頭の中のイメージを形にする構想図ができたら、次は実際にルールに沿って図を書いていくことになります。そのルールのもととなるのが「JIS(ジス)」と呼ばれるものです。
- JISは「日本産業規格(Japanese Industrial Standards)」の略で、日本の産業の基本的なスタンダード(基準)なんです。
- 製図の書き方や使う記号など、様々なルールが決められています。
- 皆さんの身の回りにある製品にも、「JISマーク」が書かれているもの、たくさんありますよ!これは、その製品がJISの基準を満たしている証拠なんです。
JISに基づいて書かれる代表的な製図の種類
このJISのルールに基づいて、私たちの技術の授業で学ぶ製図には主に3つの種類があります。それぞれの特徴と見え方を比べてみましょう。
② 全体を見せるのに適した「等角図(とうかくず)」
「等角図」は、作品の全体像を分かりやすく表すのにとても適した製図です。
- まるで、作ろうとしている物を「斜め上」から見下ろしているようなイメージで見えます。
- 立方体(箱)を想像してみてください。等角図では、その箱の「正面」と「奥」、そして「上」が同時に見えるような形で描かれます。作品全体の形を伝えるのにピッタリなんですよ!
③ 正面を正確に表す「キャビネット図」
次に「キャビネット図」です。この図は、作品の「正面の形」をとても正確に表すことができるのが特徴です。
- 図で見ると、正面はそのまま正確な形で描かれていて、奥行きや上部は斜めに表現されるイメージです。
- 正面の形が特に重要で、ここを正確に伝えたい場合に活躍する製図と言えますね。
④ 最も正確な情報を示す「第三角法による正投影図(だいさんかくほうによるせいとうえいず)」
少し名前が長いですが、これが最も詳細で正確な情報を示す製図になります。「第三角法」や「正投影図」と略して呼ばれることもありますよ。
- この製図は、作品の「正確な形」や、部品同士がどうやって「組み合わされるか(接合方法)」を細かく伝えることができます。
- 最大の特徴は、「正面から見た図」、「上から見た図」、「右から見た図」という、3つの異なる方向から見た見え方を正確に表す点です。
- それぞれ違う角度から見ることで、作品のすべての面や詳細な部分を正確に理解できるようになるんです。
まとめ
今回は、これから皆さんが作っていく作品の「設計図」にあたる「製図」の全体像について学びましたね。頭の中のイメージを形にする「構想図」から始まり、製図のルールとなる「JIS」、そして目的によって使い分ける「等角図」「キャビネット図」「第三角法による正投影図」の3種類の見え方をざっくりとですが知ることができました。
それぞれの製図には、全体を見せたい、正面を正確に伝えたい、細部まで正確に表したい、というように、表す目的が全然違うということがポイントです。次回からは、それぞれの製図の具体的な書き方について、もっと詳しく掘り下げていきますので、楽しみにしていてくださいね!
君ならできます。頑張って!
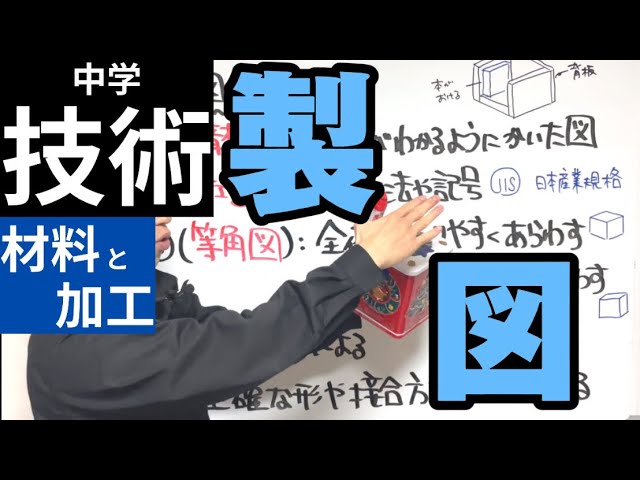


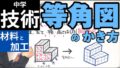
コメント