こんにちは!「おきぺん」です。
前回の授業で学んだ電気の安全と危険性の続きとして、今回は電気機器を安全に使い続けるための大切な知識をお伝えします!感電や火災の事故を防ぐ、大人になっても役立つ内容なので、しっかり一緒に学んでいきましょうね!
電気のトラブルと安全対策を理解しよう!
電気は便利ですが、誤った使い方をすると危険なことも。主な電気トラブルと、それを防ぐ安全装置について解説します。
① ショート(短絡)とは?
「ショート」は「短絡(たんらく)」とも呼ばれ、電線に異常に大きな電流が流れる現象です。誤った配線をしたり、機器が故障したりした際に、電圧差によって通常よりも大きな電流が一気に流れ込むことで起こります。「バチバチ!」と火花が出たり、そこから火災につながる危険な現象なので、とても注意が必要です。
② 隠れた火災の原因!トラッキング現象
「トラッキング現象」は、皆さんがコンセントにプラグを奥までしっかり差し込んでいない時、プラグとコンセントの隙間にホコリや湿気がたまり、それが原因で電気が漏れ(漏電)、ショートから火災につながる現象です。例えば、冷蔵庫の裏側など普段お手入れしない場所や、台所のような水回りのコンセントで起こりやすいので要注意です。これを防ぐには、プラグを奥までしっかり差し込み、定期的にコンセント周りを清掃することが大切ですよ!
③ 事故を防ぐ心強い味方!ヒューズ
「ヒューズ」は、電化製品や電気回路の中に組み込まれている電子部品です。ショートなどの事故を防ぐ役割を持っていて、もし回路に異常な量の電流が流れると、ヒューズ内部の細い電線が「パチッ」と音を立てて切れ、電気の流れを物理的に止めてくれます。これで、それ以上危険な状態になるのを防いでくれるんです!
④ 感電・漏電から守る!アース線(接地線)
皆さんの家にある電子レンジや冷蔵庫、洗濯機などの家電製品に、コンセントとは別に「緑色と黄色の線」がついているのを見たことはありませんか?それが「アース線」です!「接地線(せっちせん)」とも呼ばれますね。
アース線は地中に埋まる電線とつながっており、もし電化製品から電気が漏れてしまった(漏電した)時に、その電気を安全に地面へ逃がしてくれる役割があります。これにより、前回の授業で学んだ「感電」事故を防ぐことができるんです。アース線に電流が流れると、お家の電気を管理している「分電盤(ぶんでんばん)」にある「漏電遮断機」が作動し、自動的に電気を遮断してくれます。
⑤ 電気機器の健康診断!回路計(テスター)
最後は「回路計(かいろけい)」です。これは「テスター」とも呼ばれますね。
回路計は、電流、電圧、抵抗といった電気の基本的な性質を調べることができる道具です。電化製品がきちんと電気が通じているか、どこかで配線が切れていないか(断線していないか)などを調べるときにとても役立ちます。電化製品の保守点検には欠かせない道具なんです。
今日の学びを振り返ろう!
今回は、電気機器の安全を守るための大切な用語と、その仕組みについて学びましたね。
- 大きな電流が流れる危険な現象「ショート(短絡)」
- ホコリと湿気で火災になる「トラッキング現象」
- 異常な電流から守る「ヒューズ」
- 感電や漏電を防ぐ「アース線(接地線)」
- 電気機器の異常を調べる「回路計(テスター)」
それぞれの言葉と、その役割をしっかり理解することで、電気の事故を未然に防ぐ知識が身につきます。前回の「漏電」「感電」「ブレーカー」の知識と合わせて、混同しないように整理して覚えていきましょうね!
君ならできます。頑張って!
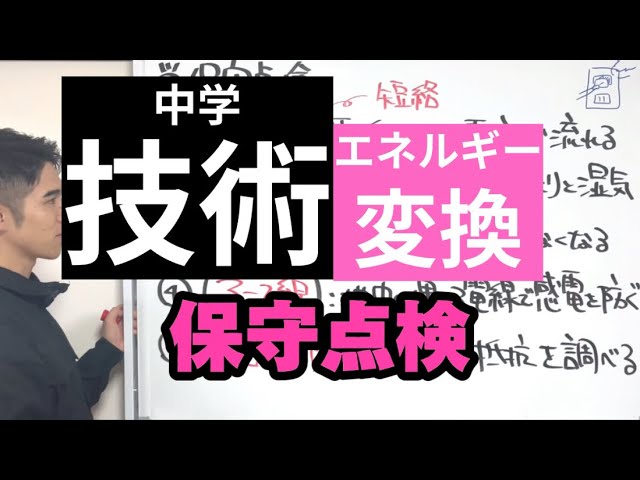



コメント