皆さん、こんにちは!おきぺんです。
技術科の授業、楽しく学べていますか?ものづくりって、奥が深くて面白いですよね!
今回は、木材加工の最初のステップ、「けがき」についてお話しします。これがマスターできれば、あなたの作品のクオリティがぐーんとアップすること間違いなしですよ!一緒にしっかり学んでいきましょう!
木材加工のスタート!「けがき」ってなんだ?
さて、ものづくりを始める上でとっても大切な工程が「けがき」です。
「けがき」とは、木材を正確に切ったり、組み立てたりするために必要な線や印を書き入れることを言います。鉛筆と定規を使って線を引くイメージですね。
「え、そんな簡単なこと?」と思うかもしれませんが、実はここがものづくりの「命」なんです!
もし、このけがきの段階で寸法を間違えてしまうと、せっかく材料を切ったり削ったりしても、最後に組み立てようとしたときに「あれ?サイズが合わない…!」なんてことになってしまいます。
だからこそ、最初の「けがき」はとっても慎重に、正確に行うことが重要なんですよ!
けがきで使う大切な2つの線
けがきでは、特に大切な2つの線が登場します。この2つの線の意味をしっかり理解しておきましょう!
① 切断線(せつだんせん)
これは読んで字のごとく、「のこぎりで切る線」のことです。「材料取り線(ざいりょうどりせん)」ということもあります。
動画の図で言うと、真ん中にある黒い線がこれにあたりますね。
「ここを切ればいいんだな!」と一目でわかる、一番わかりやすい線です。
② 仕上がり寸法線(しあがりすんぽうせん)
「切断線だけあればいいんじゃないの?」と思った人、いるかもしれませんね。
でも、のこぎりで木材を切るときって、線の通りにピッタリ0mmの幅で切れる人って、ほとんどいないんです。
のこぎりの刃自体にも厚みがありますし、どうしても少し曲がってしまったりしますよね。
そこで登場するのが、この「仕上がり寸法線」なんです!
仕上がり寸法線は、切断線の両側に引く青い線のことで、ここが「最終的に削って仕上げる目標の線」になります。
この線があることで、のこぎりで切った後に、ヤスリなどで削って正確な寸法に仕上げることができるようになるんです。
この「切りしろ」や「削りしろ」と呼ばれる、あらかじめ余分に設けておく幅は、だいたい3mmから5mmくらいが目安だと覚えておきましょう。
けがきに欠かせない!「差し金」の使い方
正確なけがきには、特別な工具が必要です。それが「差し金(さしがね)」です。
差し金ってどんな工具?
差し金は、直角(90度)の形をした金属製の工具です。
学校の実習で実際に触ってみると「なるほど!」と納得するはずです。
ちなみに、差し金に似た小さい工具で「直角定規(ちょっかくじょうぎ)」というものもありますよ。
差し金には、長い部分と短い部分があって、それぞれ名前があります。
- 長い方:長手(ながて)
- 短い方:妻手(つまで)
この長手と妻手、どちらも実習でよく使う言葉なので、ぜひ覚えておいてくださいね!
差し金を使ったけがき方
では、実際に差し金を使って線を引く方法を見ていきましょう。
- まず、木材の「基準面(きじゅんめん)」を決めます。これは、寸法を測る際の「スタート地点」になる大切な面のことです。
- 次に、差し金の長手の「内側」を、決めた基準面にピッタリとくっつけます。利き手が右利きなら、左手でしっかり押さえると安定しますよ。
- そして、妻手の「外側」に沿って、鉛筆で線を引いていきます。
なぜこの方法で線を引くのかというと、差し金は長手と妻手が必ず直角(90度)になるように作られているからです。
基準面に長手の内側をぴったり合わせることで、いつでも正確な直角の線を引くことができる、というわけですね!
差し金はとても繊細な工具なので、変形させたり叩いたりしないように、優しく扱いましょう。
慣れると、普通の物差しよりもずっとスムーズに90度の線を引けるようになりますし、目盛りもあるので寸法を測ることもできますよ。
まとめ
今回は、木材の「けがき」について、その意味や、なぜ「切断線」と「仕上がり寸法線」の2つの線が必要なのか、そして「差し金」という工具の使い方やその名前まで、たくさんのことを学びましたね。
「けがき」は、ものづくりの最初の、そして最も大切なステップです。ここがしっかりできると、後の切断や組み立てがぐっと楽になり、仕上がりも美しくなりますよ!
君ならできます。頑張って!
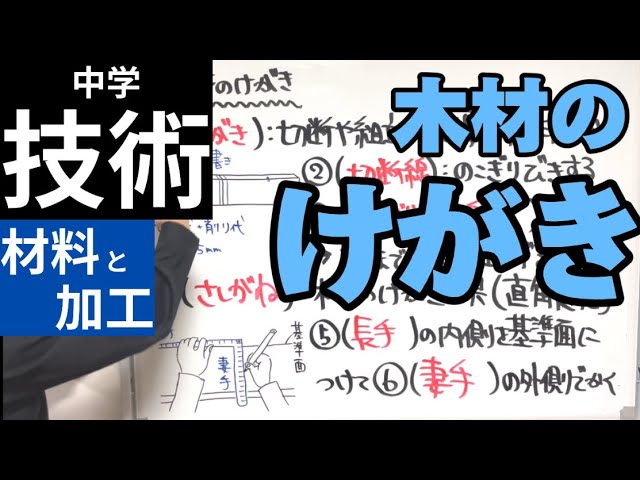


コメント