皆さん、こんにちは!「おきぺん」です!
前回の授業では木材を「切る」ことについて学びましたが、今回は「削る」作業に焦点を当てていきましょう。特に、木材加工の代表的な工具である「かんな」を使った「かんながけ」について、詳しく解説していきます。学校によってはかんなを使わないところもあるかもしれませんが、知っておいて損はない大事な内容ですよ!
かんなってどんな工具?〜木材を仕上がり寸法にするプロ〜
かんなは、簡単に言うと「木材をきれいに削って、最終的なぴったりの大きさ(仕上がり寸法)にするための工具」なんです。のこぎりで木を切っただけだと、切り口がガタガタだったり、少し余分な部分が残っていたりしますよね?かんなは、その余分な部分(切るためのゆとり分として残した2〜3mmくらいの部分)を削って、ツルツルに仕上げるために使うんですよ。
かんなの主要パーツを知ろう
かんなは、まるで大きな板に金属の刃物が2枚くっついているような形をしています。特に重要なパーツがこの2つです!
- かんな身(かんなみ):これが主役!木材を実際に削る一番目立つ大きな金属の刃物です。
- 裏金(うらがね):かんな身をサポートする役割の金属です。この裏金とかんな身がセットになって初めて、木材をきれいに削ることができるんですよ!
かんなの刃先(はさき)は、この裏金とかんな身のセットの一番下から少しだけ出ていて、かんなを手前に引くことで木材が削れる仕組みになっています。
刃先の調整ってどれくらい?〜職人技の世界〜
かんなの刃先は、なんと0.05mmから0.1mmという、ものすごくわずかな量だけ出すように調整するんです。これは本当に繊細な作業で、まさに職人技のレベルなんですよ!
- 刃を出すとき:かんな身の頭の部分を玄能(げんのう)やハンマーで「カンカンカン」と軽く叩きます。
- 刃を引っ込めるとき(または刃全体を抜くとき):かんな本体の「台頭(だいがしら)」(手で持つ側の先端部分)を左右に「コンコンコン」と叩くと、かんな身と裏金がスポッと抜けるんです。
刃を出すときと抜くときで叩く場所や方法が違うので、この点はしっかり覚えておきましょうね!
かんながけの削り方〜木目の向きがポイント!〜
実習で皆さんがよく行うかんながけには、主に2つの削り方があります。どちらも木材の「繊維の向き(木目)」を意識することがとっても大切です!
小口削り(こぐちけずり)
「小口」というのは、木材の繊維の方向に垂直な部分のことです。ちょうど、ストローを真上から見たような断面をイメージしてみてくださいね。ここを削るのが「小口削り」です。
小口を削る時は、気をつけないと木材の繊維が「バリバリバリッ」と割れてしまう「いわれ」という現象が起きやすいんです。これを防ぐために、一気に削り切るのではなく、まず片面を削ったら、残りの約3分の1くらいを削るために木材をひっくり返して削るようにしましょう。
木端削り(こばけずり)
一方、「木端」というのは、木材の繊維の方向に平行な部分のことです。ストローを横から見たような、長ーい側面をイメージすると分かりやすいですね。ここを削るのが「木端削り」です。
木端削りは小口削りに比べて、比較的簡単にできます!繊維の方向に沿って削るので、「いわれ」が起きる心配もほとんどありません。なので、力を入れて最後まで一気に引き切ってしまって大丈夫ですよ。
実習では、もしかしたら小口削りをする機会の方が多いかもしれませんね。それぞれの削り方の特徴とコツをしっかり覚えて、実践してみてください!
まとめ
今回の記事では、木材加工の仕上げに欠かせない工具「かんな」について、そのしくみや使い方、そして代表的な2つの削り方について学びました。
- かんなは、木材を「仕上がり寸法」にするための工具であること。
- 「かんな身」と「裏金」の2つの刃物がセットで機能すること。
- 刃先の調整は0.05〜0.1mmととても精密で、出し方と抜き方(引っ込め方)があること。
- 木材の繊維に垂直な「小口」を削る「小口削り」と、繊維に平行な「木端」を削る「木端削り」があること。
かんながけは、初めてだと難しく感じるかもしれませんが、ポイントをしっかり押さえれば誰でもきれいに削れるようになります。教科書も参考にしながら、ぜひ挑戦してみてくださいね!
君ならできます。頑張って!
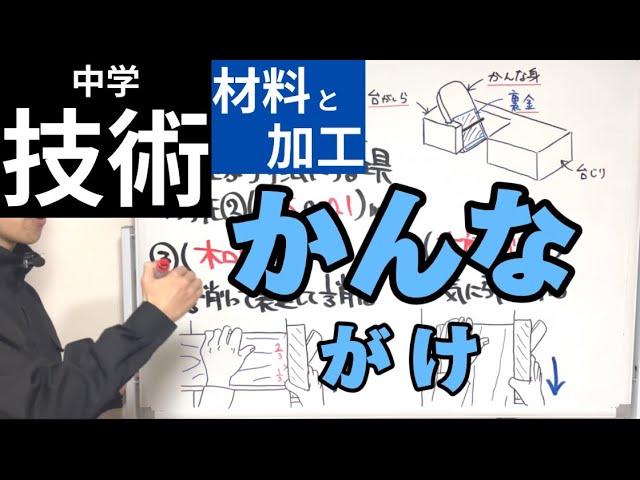



コメント