はい、こんにちは!おきぺんです。
今回の内容は「電源」についてですが「電源」って聞くと、ちょっと難しそうに感じるかもしれませんね。でも大丈夫!私たちが普段使っている乾電池や、家にあるコンセント。実は、これらには私たちの生活を支える大切な秘密が隠されているんですよ。この秘密を一緒に解き明かしていきましょう!きっと「なるほど!」って感動するはずです。
電源ってどんな種類があるの?
技術の授業で「電源」について学ぶとき、大きく分けて2つの種類があることを知っておくと、グッと理解が深まります。それは、「電池」と「家庭用電源」です。同じ電気を供給するものでも、それぞれに面白い特徴があるんですよ!
① みんなの身近にある「電池」のヒミツ
まず、みんなが普段よく使う「電池」についてです。スマートフォンや携帯ゲーム機など、身の回りには電池で動くものがたくさんありますよね。
電池の大きな特徴は、電気の流れる向きが「常に一定」だということ。これを専門用語で「直流」と呼びます。グラフで表すと、まるで一直線に進んでいくように、電圧がいつも同じ向きで保たれているイメージです。乾電池なら「1.5Vがずっとキープされる」という感じですね。
この電池、実はさらに2つのタイプに分けられるんです!
- 一次電池(使い切りタイプ)
- これは「一度使ったら終わり」の電池のことです。電圧が低くなると、もう使えなくなってしまいます。
- 例えば、100円ショップで売っているアルカリ電池やマンガン電池などがこれにあたりますね。懐中電灯や時計によく使われています。
- 二次電池(充電できるタイプ)
- こちらは、何度も繰り返し充電して使えるとっても便利な電池です。
- 身近な例でいうと、みんなが毎日使っているスマートフォンのバッテリーや、携帯ゲーム機の電池がこの二次電池なんですよ。充電できるから、エコで経済的でもありますね!
これが電池の種類になります。基本的に、電気の向きが一定なのが電池の特徴です。
② お家で使う「家庭用電源」のヒミツ
次に、家にあるコンセントから供給される「家庭用電源」についてです。これは電池とは少し違う面白い特徴を持っています。
家庭用電源は、電気の流れる向きが「時間とともに周期的に変わる」という特徴があります。これを「交流」と呼びます。グラフで見ると、プラスとマイナスの間を行ったり来たり、まるで波のように動いているのがわかります。つまり、電気が行ったり来たり、行ったり来たりしているのが家庭用電源の交流なんです。
この交流、実は地域によって電気の「周波数」というものが違うんです。周波数というのは、「1秒間に電気の向きがどれくらい変わるか」を示す数字のこと。
- 東日本: 50Hz (ヘルツ)
- これは1秒間に50回、電気の向きが変わっているということです。
- 西日本: 60Hz (ヘルツ)
- こちらは1秒間に60回、電気の向きが変わっているんですよ。
「え、どうして日本の中で違うの?」って思いますよね。実はこれ、明治時代に日本に導入された発電機のタイプが、東日本はドイツ製、西日本はアメリカ製だったことに由来しているんです。その名残が今も残っているというのは、ちょっとした豆知識ですね!
充電に欠かせない!「ACアダプター」って何?
ここで「あれ?」と思った人もいるかもしれませんね。スマートフォンやゲーム機を充電するとき、家庭のコンセントに直接挿すだけじゃなくて、途中に四角いゴツい箱のようなものが付いていますよね。あれが「ACアダプター」なんです。
なぜ必要かというと、ゲーム機のような二次電池は「直流」で充電されるのが一番効率がいいんです。でも、家庭用電源は「交流」ですよね。交流のままだと、電気が行ったり来たりするので、うまく充電できません。そこで、ACアダプターが家庭の「交流」の電気を、充電しやすい「直流」の電気に変えてくれているんですよ。賢い仕組みですよね!
まとめ
今回は、身近にある「電源」について、その種類と特徴を詳しく見てきました。
- 電池は、電気の向きが一定の直流。使い切りの一次電池と、充電できる二次電池があることを学びましたね。
- 家庭用電源は、電気の向きが周期的に変わる交流。東日本と西日本で周波数が違うことも知りました。
- そして、交流を直流に変えてくれるACアダプターの役割も分かりましたね。
これらの知識は、技術の授業だけでなく、日常生活でも役立つことばかりです。電気の仕組みを知ることで、家電製品をより安全に、そして賢く使えるようになりますよ。
君ならできます。頑張って!
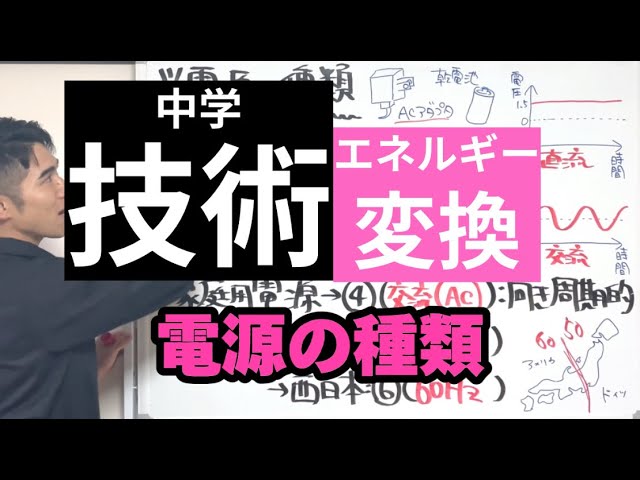
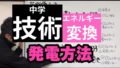

コメント