皆さん、こんにちは!「おきぺん」です。元中学校技術科教員として、このYouTubeチャンネル「ギリギリ技術」で、いつも皆さんに技術の解説動画を発信しています。
さて、前回の電気回路のお話、覚えていますか?家電製品の内部の仕組みについて、ざっくりと学びましたね。今回はその続き、特に「回路図」について、もっと詳しく掘り下げていきましょう!回路図は、電気の通り道を示す「設計図」のようなもので、これが読めると家電製品の動きもイメージしやすくなりますよ。少し難しそうに感じるかもしれませんが、一緒にポイントを押さえていけば大丈夫!さあ、早速始めていきましょう!
電気回路の基本ブロックをおさらい!
前回の授業でも少し触れましたが、電気回路は大きく3つのブロックで構成されています。回路図を理解する上でも、この3つの役割をしっかりイメージすることが大切ですよ。
電源のブロック
これは、電気を供給する部分です。例えば、コンセントや電池などがこれにあたりますね。電気がなければ何も始まりませんから、一番大切なスタート地点です。
負荷のブロック
電気を使って何かをする部分です。モーターや電球など、電気エネルギーを別のエネルギー(光や運動など)に「変換」する役割を担っています。
制御のブロック
電気の流れをコントロールする部分です。スイッチなどがこれにあたりますね。電気を流したり止めたり、電気の量を調整したりと、回路の動きを司ります。
これだけは覚えよう!7つの電気用図記号
回路図を書くには、それぞれの電子部品を表す「電気用図記号」を知る必要があります。今回は、特に重要な7つの記号をしっかりマスターしていきましょう!
電池(乾電池)
一番基本的な電源の記号ですね。長い線がプラス(+)、短い線がマイナス(-)を表します。ここから導線が伸びていくイメージです。
電源プラグ
コンセントから電気を取り込む部分です。この記号から導線が伸びていきます。
【ここがポイント!】
直流電源(乾電池など)にはプラスとマイナスがありますが、家庭用の交流電源(コンセントなど)にはプラス・マイナスがないんです。これは、電気が行ったり来たりしているからなんですね。
ランプ(電球)
光を発する部品の記号です。丸の中にバツ印が書かれているような形をしていますね。小学校でも習ったことがあるかもしれません。
モーター
電気で物を動かす部品です。記号は丸の中に「M」と書きます。これは「Motor」の頭文字ですね。扇風機の羽根を回したり、おもちゃの車を動かしたりするのに使われます。
LED(発光ダイオード)
「発光ダイオード」と呼ばれる、光る部品です。特徴的な記号で、一つだけ注意してほしいことがあります。
【ここがポイント!】
LEDは電気を流す向きが決まっています。プラスから出てきた電気が、記号の矢印の方向に流れるように接続しないと光りません。また、光が出ていることを示す二つの小さな矢印が記号の外側に付いているのも特徴です。シンプルな「ダイオード」という電子部品もありますが、そちらにはこの光を示す矢印は付きませんよ。
スイッチ
電気の通り道を開いたり閉じたりする記号です。オン・オフを切り替えるイメージですね。回路を「繋いだり」「閉じたり」することで、電気の流れをコントロールします。
抵抗器
流れる電気の量を調整する役割を持つ部品です。長方形のような形をしていますね。理科の授業でも出てくることが多いので、しっかり覚えておきましょう。
実践!扇風機の回路図を描いてみよう
さあ、覚えた記号を使って、身近な家電製品である「扇風機」の回路図をイメージしてみましょう!
扇風機の部品を分解!
まず、扇風機がどんな電子部品でできているかを想像します。主な部品は次の3つですね。
- コンセントにつなぐ「電源プラグ」
- オン・オフを切り替える「スイッチ」
- プロペラを回す「モーター」
回路図の描き方ルール
これらの部品を使って回路図を描くには、重要なルールがあります。それは「それぞれの部品が、1本の導線で結ばれている状態」で初めて正しく機能する、ということです。電気は回路の中をぐるっと一周する道がないと流れません。
具体的には、電源プラグから出てきた導線がスイッチにつながり、そこからモーターへ。そしてモーターから再び電源プラグへと戻るように、きれいな四角形で導線をつないでみましょう。これが扇風機の回路図のモデルになりますね。
よくある間違いに注意!
「家電製品はコンセントから一方的に電気をもらっている」と考える人もいるかもしれませんが、実はそうではありません。導線でしっかりとつながって、電気が通る「道」ができていなければ、電気は流れないのです。これは交流の電気でも同じなので、ぜひ覚えておいてくださいね。
今回のまとめ
どうでしたか?今回は、電気回路の「設計図」である回路図について、じっくり学びましたね!
- 電気回路が「電源」「負荷」「制御」の3つのブロックでできていること。
- それぞれの部品を表す「電気用図記号」の7つの種類と役割。
- 身近な扇風機を例に、回路図の描き方と大切なルール。
これらの知識は、技術の授業だけでなく、理科の電気分野の学習にもつながっていきます。教科書やワークで、他の電子部品の記号を確認したり、色々な回路図を描く練習をしたりして、知識を自分のものにしてくださいね!
君ならできます。頑張って!
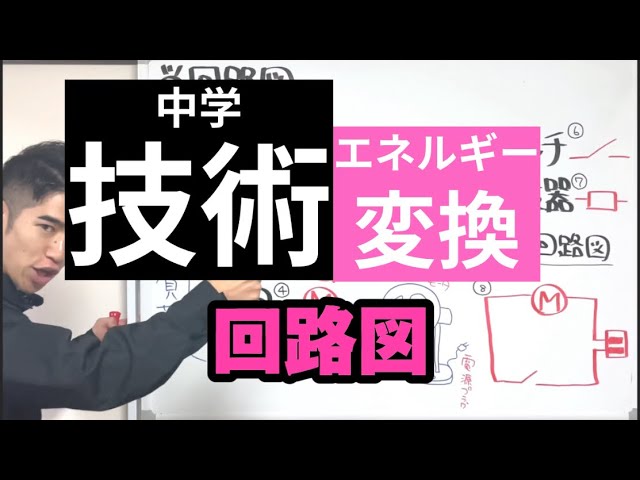



コメント