こんにちは!YouTubeチャンネル「ギリギリ技術」を運営している、元中学校技術科教員のおきぺんです!
みなさん、普段の生活の中で「これ、どうして自動で動くんだろう?」って思ったことはないかな?例えば、人が通るとパッと電気がつく廊下や、部屋の温度を快適に保ってくれるエアコンとか。実は、これらの「自動で動く」ものには、私たちの生活を便利にしてくれる「計測・制御システム」という仕組みが隠れているんです!今日は、このすごいシステムについて、一緒に楽しく学んでいきましょうね!
計測・制御システムって何だろう?
身の回りの「自動化」の仕組み
計測・制御システムは、簡単に言うと「外から情報を受け取って、コンピュータが判断し、自動で何かを動かす」システムのことなんです。今までプログラミングについて学んできた人もいると思いますが、そのプログラムを使って、身の回りのものを「自動化」したり、「制御」したりする仕組みや流れを学んでいきます。
具体例:車の自動ブレーキシステム
イメージしやすいように、車の「自動ブレーキシステム」を例に考えてみましょう。もし車が障害物に近づきすぎたら、自動でブレーキがかかるシステムのことです。これがどうやって動いているのか、気になりませんか?大きく分けると、次の6つのステップで動いているんですよ!
計測・制御システムの6つの要素
1. センサ:情報をキャッチ!
まず最初に、周囲の情報を測るのが「センサ」です。車の自動ブレーキの例だと、センサが車と障害物との「距離」を測っています。もし距離が近づいた、という情報をキャッチするわけですね。他にも、外の「明るさ」や「温度」などを読み取るセンサが、私たちの身の回りにはたくさんありますよ。例えば、人が通ると自動でライトがつくのも、エアコンが室温を取り込むのも、センサのおかげなんです!
2. インターフェース(入力):アナログからデジタルへ!
センサがキャッチした情報は、実は「電気信号」という連続的な「アナログ情報」の状態なんです。例えるなら、なめらかな音の波みたいなイメージかな。でも、コンピュータはこのアナログ情報をそのままでは処理できません。そこで登場するのが、このインターフェースです!インターフェースは、アナログ情報をコンピュータが理解できる「デジタル情報(0と1のデータ)」に変換する役割を持っています。これを「AD変換」と言ったりもします。
3. コンピュータ:司令塔の役割!
デジタル情報に変換されたデータは、次に「コンピュータ」に送られます。コンピュータは、まさにシステム全体の「司令塔」!集まったデジタル情報をもとに、「危ない!ブレーキをかけよう!」といった判断をして、新しい命令を出すんです。私たちが以前学んだCPU(中央処理装置)が、ここで大活躍しているわけですね。
4. インターフェース(出力):デジタルからアナログへ!
コンピュータが出した命令は、まだデジタル情報のままです。このデジタル命令を、今度は実際に機械を動かすための「電気信号(アナログ情報)」に戻す必要があります。そう、またしてもインターフェースの登場です!今度はデジタル情報をアナログ情報に変換する、逆の役割をしてくれるんですね。これを「DA変換」と呼ぶこともありますよ。
5. アクチュエータ:実際に動かすところ!
アナログ情報に戻された命令は、いよいよ「アクチュエータ」に伝わります。アクチュエータは、その命令を受けて、実際に「仕事」をする部分のことなんです!車の自動ブレーキの例では、アクチュエータが「ブレーキをかける」という動作を行い、車をピタッと止めてくれるわけです。エアコンの例だと、設定した温度に合わせて、エアコンが涼しい風を出したり、暖かい風を出したりする部分がアクチュエータになりますね。
どうですか?この6つの要素が、まるでリレーのように情報をバトンタッチしながら、私たちの知らないところで自動で動いてくれているんですね!
プログラミングによる課題解決の流れ
計測・制御システムの開発に限らず、何か問題を見つけて解決していくには、実は決まった流れがあります。これはプログラミングの世界でも同じなんですよ!
- 問題を発見する:まず「ここがうまくいかないな」「もっと良くするにはどうしたらいいだろう」という問題を見つけます。
- 課題を設定する:見つけた問題の中から「よし、これを解決しよう!」という具体的な目標(課題)を決めます。
- 設計する:その課題を解決するために「こんな方法でやってみよう」という計画を立てます。
- 制作する:設計した計画をもとに、実際にプログラムを作ったり、システムを組み立てたりします。
- 評価・改善する:作ったものがちゃんと動くか試して(評価)、もしうまくいかなかったら「もっとこうしたら良くなるんじゃないかな?」と考えて修正(改善)します。この繰り返しが、より良いシステムを作る秘訣なんです!これはPDCAサイクルに似ていますね。
修正作業「デバッグ」って知ってる?
プログラムを作っていると、どうしても「バグ」と呼ばれる間違いやエラーが出てきてしまうことがあります。そんなとき、このバグやエラーを見つけて、プログラムを直す作業のことを「デバッグ」と言います。デバッグは、プログラミングではとても大切な作業なので、ぜひ覚えておいてくださいね!
まとめ
今日は、身の回りの自動化を支える「計測・制御システム」について学びました。センサで情報をキャッチし、インターフェースで変換、コンピュータで判断し、再びインターフェースで変換して、アクチュエータが動く、という一連の流れが分かったでしょうか?
そして、システム開発の流れや、プログラムの修正作業である「デバッグ」についても理解が深まったら嬉しいです!
君ならできます。頑張って!
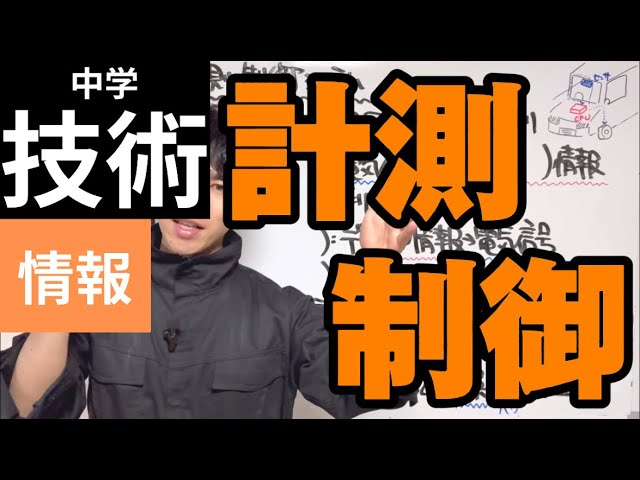


コメント