こんにちは!元中学校技術科教員のおきぺんです。YouTubeチャンネル「ギリギリ技術」も運営しています!
今回の記事は、みんなが技術科で学習する「材料と加工の技術」の中から、特に「切断」にスポットを当てて解説していきますね!前回の木材の切断(のこぎり)に続いて、今回は、木工機械(糸のこ盤)、金属、プラスチックの切断方法について、動画の内容をギュッとまとめてお届けします。きっと、テスト勉強にも役立つはず!一緒に頑張りましょう!
さまざまな材料の切断方法を学ぼう!
材料を切断するって言っても、その材料によって使う工具も、その使い方も全然違うんです。今回は、特に中学校の技術科でよく出てくる以下の4つの切断方法について、詳しく見ていきましょう!
- 木工機械(糸のこ盤)
- 金属の切断(金切りバサミ)
- 金属の切断(弓のこ)
- プラスチックの切断(プラスチックカッター)
木材を切る機械!「糸のこ盤」ってどんなもの?
まず最初に紹介するのは、木工機械の「糸のこ盤(いとのこばん)」です。これまで学習した「両刃のこぎり」は主にまっすぐな直線切断に使うことが多かったですよね。でも、ものづくりをしていると「カーブに切りたいな」「真ん中だけくり抜きたいな」なんて思うこと、ありませんか?そんな時に大活躍するのが、この糸のこ盤なんです!
糸のこ盤の最大の特徴は、主に曲線や切り抜きをする時に使われることです。名前の通り、「糸」のように細い「のこ」の刃(糸のこ)がついています。この糸のこが、テーブルの上で激しく上下に動き、その動きを利用して材料を切断していくんですよ。
使い方としては、材料(木材やプラスチック)をテーブルにしっかりと押し付けて、切断したい線に沿ってゆっくりと材料を押し進めていくだけ!すると、カーブでも複雑な形でも、きれいに切ることができるんです。
安全面もとっても大切ですよ。学校で習うと思いますが、保護メガネの着用や、作業が終わった後の切りくずの片付けなど、安全に関する指示はしっかり守ってくださいね。
薄い金属を切るなら!「金切りバサミ」の使い方
続いては金属の切断です。金属を切る工具、その名も「金切りバサミ(かなきりバサミ)」!名前の通り、金属を切るハサミです。これは薄い金属板を切る時に使います。
使い方は、通常のハサミと基本は同じですが、金属は硬いので、けっこう力が必要です。ポイントは、刃の先端ではなく、根元から中央にかけて使って、ガシガシと切っていくこと。そして、切っている方の金属を少し持ち上げながら切ると、切りやすくなりますよ。最後の切り終わりは、パチンと切るのではなく、ねじって終わるのがスタンダードな使い方なんです!ちょっとテクニックがいりますが、慣れるとスムーズに切れるようになりますよ。
厚みのある金属を切るなら!「弓のこ」の使い方
次に、金属の棒材など、少し厚みのある金属を切る時に使うのが「弓のこ(ゆみのこ)」です。弓のこは、両手でしっかり握って使います。
木材のこぎり(両刃のこぎり)は引くときに力を入れましたが、弓のこは全く逆!押す時に力を入れて切るのが特徴です。なので、のこぎりの刃の向きも、奥側(押す方向)に鋭くなっているんですよ。切る時は、手だけでゴシゴシするのではなく、体全体で体重をかけながら切ると、楽に、そして安全に切ることができます。
プラスチックを切るなら!「プラスチックカッター」の使い方
最後は、薄いプラスチック板を切る時に使う「プラスチックカッター」です。これも名前の通りですね!形は普通のアートナイフやカッターナイフに似ていますが、先端がプラスチックを切るのに特化した作りになっています。
使い方は、カッターと同じように、引く時に力を入れます。プラスチック板に何回かカッターを引いて、板の厚さの3分の1くらいまで溝(みぞ)をつけましょう。溝ができたら、テーブルの端っこなど、角がある場所に溝を合わせて、パキッと折るようにして切断します。これがプラスチックカッターの基本的な使い方なんです!
今回の学習のまとめ
今回は、木工機械(糸のこ盤)、金属(金切りバサミ、弓のこ)、プラスチック(プラスチックカッター)の様々な切断工具とその使い方について見てきましたね。それぞれの材料に合った工具を選び、正しい使い方をすることで、安全に、そしてきれいに材料を切断することができます。
今回の内容で、各工具の特徴や使い方、注意点などは、学校の教科書でしっかり確認しておいてくださいね!テストで出やすいポイントなので、しっかり理解を深めておきましょう!
君ならできます。頑張って!
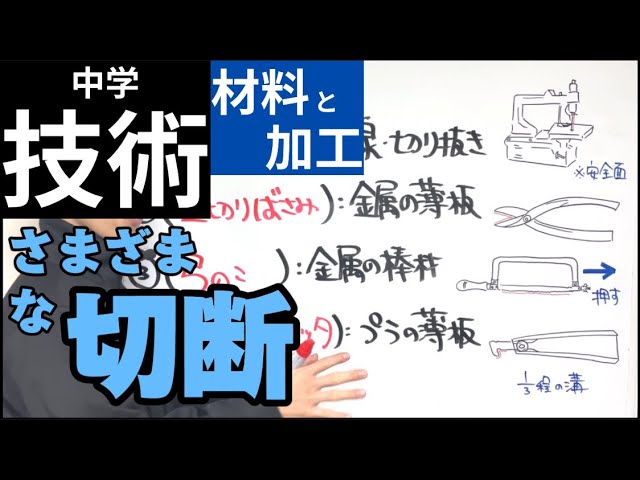


コメント