こんにちは、おきぺんです!元中学校技術科教員として、そしてYouTubeチャンネル「ギリギリ技術」の管理人として、今回はみんなが技術の授業でチャレンジする「はんだづけ」について、一緒に詳しく見ていきましょう!
金属を溶かして部品同士をつなぎ合わせるって、なんだか難しそう、と思うかもしれませんが、実はきちんとした手順とポイントを押さえれば、誰でも上手にできるようになるんですよ。エネルギー変換の技術を学ぶ上でとっても大切なこの実習、一緒にマスターしていきましょうね!
はんだづけって、どんな技術?
はんだづけは、電子部品などを基板に固定したり、電気を通すための回路を作るためによく使われる技術です。金属を「溶かして」くっつけるのがポイントなんですよ。
はんだってどんなもの?
実習で細長い金属の棒をもらうと思いますが、それが「はんだ」です。はんだは、実は二つの金属が混ざり合ってできた「合金(ごうきん)」なんです。
- 材料は?:主に「錫(すず)」と「鉛(なまり)」という金属が特定のバランスで混ざり合っています。
- 特徴1:煙は有害!:はんだを溶かす時に白い煙が出ますが、これ、実は有害な煙なんです。しかも、めちゃくちゃ臭いんですよ!だから、実習の時は必ず換気(かんき)をしっかりしてくださいね。直接吸い込まないように注意しましょう。
- 特徴2:融点(ゆうてん)が低い!:「融点(ゆうてん)」というのは、固体(固まっている状態)から液体(溶けた状態)に変わる温度のことです。はんだの融点はなんと約200℃なんです! 錫と鉛、それぞれの金属はもっと高い温度でしか溶けないのですが、ある比率で混ぜると、不思議なことに溶ける温度がぐっと低くなるんですよ。だからこそ、はんだは金属の接着や溶接(ようせつ)によく使われるんですね。
はんだごてってどんな道具?
はんだごては、その名の通り、はんだを溶かすための「コテ」のような道具です。見た目は手で持てるくらいの大きさですが、先端はとーっても熱くなります。
- 先端の温度は?:はんだごての先端は、なんと300℃以上にもなります! はんだの融点が約200℃でしたよね? はんだごての先端が300℃以上になるからこそ、はんだを当てるとすぐに溶ける、というわけです。
- 注意点!:はんだごての電源を入れてすぐに、はんだを当てても、まだ温度が200℃を超えていないとはんだは溶けてくれません。しっかり温まってから使うようにしてくださいね。
失敗しない!はんだづけの5つのステップ
はんだづけは、正しい順番で作業することがとっても大切です。次の5つのステップをしっかり守って、上手にはんだづけを成功させましょう!動画でもこの順番が分かりやすく説明されていましたね。
ステップ1:まずは接着部を温める!
はんだごてのコテ先を、基板にある「ランド」と呼ばれる部分や部品の足など、部品と基板の「接着部(せつごうぶ)」にしっかり当てて、まずはそこを温めます。まるで部品に「さあ、はんだが来るよ!」と準備させているイメージですね。ここを温めておくことで、はんだがスムーズに流れやすくなり、しっかりと部品にくっついてくれるんですよ。
ステップ2:はんだを流し込む!
接着部がしっかり温まったら、その温めているコテ先のすぐ近くに、はんだをゆっくりと当ててみてください。コテ先が十分な温度(300℃以上)になっていれば、はんだは白い煙を出しながら、スルスル〜っと溶けて流れていきます。この時出る煙は、有害なので吸い込まないように気をつけてくださいね。
ステップ3:はんだを先に離す!
溶けたはんだが「このくらいかな」という適量(てきりょう)になったら、まず、はんだをコテ先から離してください。ここが重要ポイント!決してはんだごてを先に離してはいけません。
ステップ4:最後に、はんだごてを離す!
はんだを離したら、次に、はんだごてのコテ先を接着部から離します。この時、溶けたはんだがしっかりと部品にのっているか、結合部が完成しているかを確認してから離すようにしましょう。
ステップ5:不要な部分をカット!
最後に、部品の足などの「芯線(しんせん)」や、接着部の余分な部分があれば、「ニッパー」という工具を使ってパチッと切り落とします。これで見た目も美しく、しっかりとしたはんだづけの完成です!
これらの5つのステップ、特に順番は絶対に間違えないようにしてくださいね!「コテ先をつけて温める → はんだを流す → はんだを離す → コテ先を離す → ニッパーで切る」この流れを体に覚え込ませましょう。
まとめ
今回は、技術科の授業で必ず出てくる「はんだづけ」について、その材料であるはんだと使う道具のはんだごての仕組み、そして最も大切な5つの作業ステップを学びました。それぞれの特徴や注意点を理解して、実習に臨む準備はバッチリですね!
これらの知識は、実習のテストや技能のテストで問われることも多いので、動画の内容をしっかり復習して、自信を持って取り組んでください!
君ならできます。頑張って!
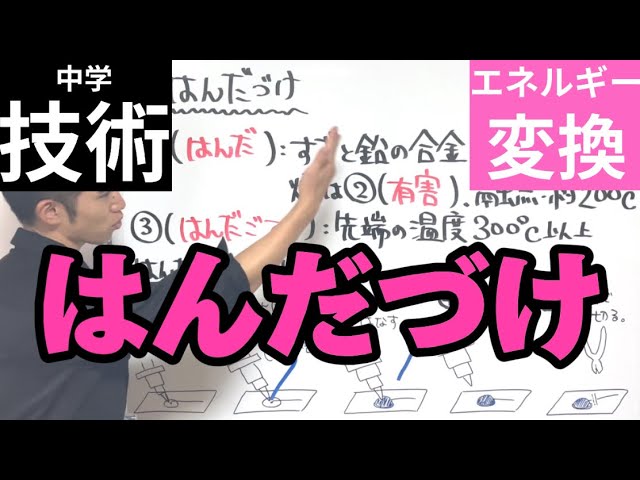


コメント