こんにちは、みんな!「ギリギリ技術」のおきぺんです!
中学校の技術科の授業で、たくさんの機械が出てきて「これ、どうなってるの?」って思ったことはありませんか?実は、私たちの身の回りにある機械の多くは、エネルギーを形を変えて利用しているんです。今回は、そんなエネルギー変換の技術の中から、特に「熱機関」というものについて、一緒に楽しく学んでいきましょう!
熱機関ってなんだろう?
熱機関とは、ズバリ!「熱エネルギーを運動エネルギーに変換する機械」のことなんです。ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、つまり「あったかい熱の力を使って、物を動かす」仕組みのことなんですね。
熱エネルギーから運動エネルギーへ
熱機関の一番大切な役割は、熱のエネルギーを、物を動かす運動のエネルギーに変えることです。例えば、水を温めると水蒸気が出ますよね?この水蒸気の「圧力」を使って、ぐーっと物を押し動かすことで、運動エネルギーとして利用するんですよ。
身近な熱機関の例
熱機関と聞くと、ちょっと遠い存在のように感じるかもしれませんが、実はとっても身近なところにあります。代表的なもので言うと、昔の蒸気機関車(蒸気機関)や、みんなの家の車に入っているガソリンエンジン(ガソリン機関)などが、この熱機関の仲間なんですね。熱を使って何かを動かしているものは、だいたい熱機関だとイメージしておけばOKです!
タービンで電気を作る!
私たちが普段使っている電気も、実は熱機関の力を借りて作られていることがほとんどなんです!
蒸気タービンって?
熱機関の中でも特に電気を作るのに活躍するのが「蒸気タービン」です。これは、高温・高圧になった水蒸気の勢いで、まるでプロペラのように「タービン」という羽根車をぐるぐる回す仕組みになっています。タービンが回ると、その先についている発電機も一緒に回って、電気エネルギーが生み出されるんです。この電気は、私たちの家に送られてくる家庭用の電源として使われているんですよ。
火力発電と原子力発電の仕組み
実は、日本の電気の多くをまかなっている火力発電や原子力発電も、基本的にはこの蒸気タービンを使って電気を作っています。燃料を燃やしたり、原子力の力を使ったりして水を熱し、蒸気を作ってタービンを回しているんですね。
最新の発電方法!コンバインドサイクル発電
最近では、もっと効率よく電気を作るための「コンバインドサイクル発電」という方法が注目されています。
ガスと蒸気のいいとこどり!
「コンバインド」は「組み合わせる」、「サイクル」は「回る」という意味なので、まさに「いろんなものを組み合わせて、ぐるぐる回す発電」という感じですね!この発電方法は、先ほど出てきた蒸気タービンに加えて、ガスタービンというものを組み合わせているのが特徴です。
ガスタービンは、天然ガス(LNGなど)を直接燃やして、その燃焼の力でタービンを回します。イメージとしては、ジェットエンジンのようなものです。
なぜすごい?排熱の有効活用
コンバインドサイクル発電の最大のメリットは、エネルギーを無駄なく使えることです。ガスタービンを回した後に、まだ熱い「排熱(はいねつ)」が出るのですが、この余った熱を捨てるのではなく、もう一度有効活用するんです!どうするかっていうと、この排熱を使って水を温め、蒸気タービンを回すための蒸気を作るんですね。
こうすることで、一つの燃料から、ガスタービンと蒸気タービンの両方で発電できるため、とっても効率的で、無駄を減らせるんですよ。「再利用」と考えるとわかりやすいかもしれませんね!
まとめ
今回は、熱エネルギーを運動エネルギーに変える「熱機関」について学びました。特に、熱を使ってタービンを回し、電気を生み出す仕組みや、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせることで、もっと効率よく発電できるコンバインドサイクル発電についても理解が深まったでしょうか。
私たちの暮らしを支えるエネルギー技術は、日々進化しているんですね。今回の内容が、みんなの技術への興味を深めるきっかけになったら嬉しいです。
君ならできます。頑張って!
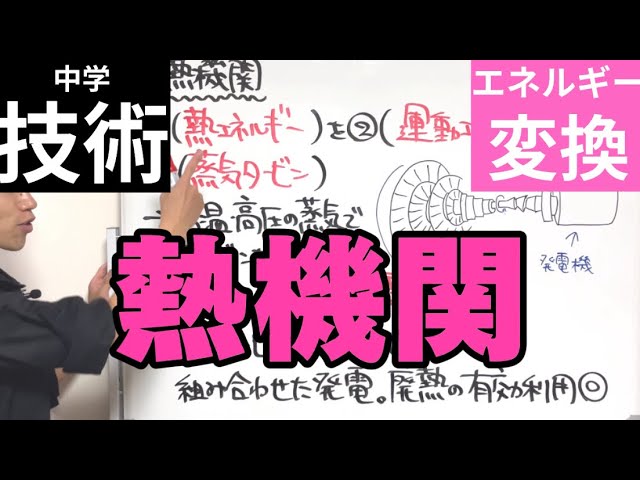
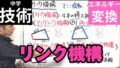

コメント