こんにちは!元中学校技術科教員のおきぺんです。今回の記事では、YouTubeチャンネル「ギリギリ技術」で解説している「キャビネット図の描き方」について、皆さんがもっと深く理解できるように、ていねいに解説していきますね。技術の授業で出てくる製図って、ちょっと難しそうに感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば大丈夫!一緒に見ていきましょう。
キャビネット図ってどんな図?その特徴を知ろう!
技術の授業で製図を学ぶとき、「等角図」「キャビネット図」「第三角法の正投影図」の3つの描き方を習うことが多いですよね。今回はその中の2つ目、キャビネット図について掘り下げていきます。
キャビネット図の「ここがすごい!」特徴
- 正面の形を正確に表せる!
キャビネット図の一番大きな特徴は、なんと言っても「正面の形がとっても見やすい」ことなんです! 箱を例にすると、箱の真正面を、まるで写真を見ているかのように正確に描くことができます。 奥の方にある、上や横からの奥行きについては、ちょっと特殊な描き方をするのがポイントなんです。 だから、「正面の形をしっかり見せたい!」というときに、このキャビネット図が選ばれることが多いんですよ。
さあ、キャビネット図を描いてみよう!手順と注意点
では、実際にキャビネット図を描くときの手順と、特に気を付けてほしいポイントを、僕と一緒に見ていきましょう!
手順1:まずは「正面」を決めよう!
立体を描くとき、最初にすることは「どこを正面にするか」を決めることです! そして、その正面の形を、そのままの形・そのままの長さで、正確に描き写してくださいね。 例えば、等角図(前回習った図ですね!)からキャビネット図に描き換えるときは、等角図の「左手前」の面を正面とすることが多いです。
動画の中では、こんな図を例に説明していましたね。横の長さが4マス、縦の長さも4マスの図形があって、その中に2マスずつへこんでいる部分がありました。 この部分を、まさにその通りに、横4マス、縦4マス、そして2マスずつのへこみもそのまま描きます。 これがキャビネット図の「正面」になる部分です。まずは、この部分を正確に描くことから始めてくださいね。
手順2:「奥行き」の描き方がポイント!45度と1/2のルール
さあ、ここがキャビネット図の一番の肝(きも)であり、間違いやすいポイントでもあるので、よーく聞いてくださいね!
奥行きを描くときは、次の2つのルールがあります。
- 45度傾けて描くこと
- 実際の長さの「1/2」の長さで描くこと
動画の例では、奥行きが4マス分ありましたよね。 この場合、1/2の長さで描くので「2マス分」の長さで描くことになります。ただし、ここで大きな落とし穴があるんです!
【超重要!】マス目と奥行きの長さについて、ここが間違いやすいんです!
製図用紙にマス目がある場合、「斜めに2マス分」進めばいいのかな?と思うかもしれませんが、これは間違いなんです! なぜかと言うと、横の1マスと斜めの1マスでは、長さが少し違うからなんですね。 斜めに2マスだと、横の2マス分よりも長くなってしまうんです。
なので、正しくはこうします。
- 実際の奥行きが「横に4マス分」の長さなら、その半分の「横に2マス分」の長さを目安にして、そこを45度斜めに進んだ場所に点を打つ、というイメージです。
つまり、マス目通りに斜めに進むのではなく、実際の長さ(ここでは「横のマス数」で考えた長さ)の半分を、45度の方向に描くということになります。 こうして点を打ったら、あとはその点と、正面の角とを線で結んでいけば、奥行きのあるキャビネット図が完成します!
最後に、製図ではマス目は描かないのが基本なので、余分な線はきれいに消して、外形だけが残るように仕上げてくださいね。 これで、バッチリなキャビネット図が描けるはずです!
まとめ:キャビネット図のポイントは「正面」と「奥行き」!
今回のキャビネット図の描き方、いかがでしたか?重要なポイントは、この2つです!
- 正面の形は、そのままの形で正確に描く!
- 奥行きは、45度に傾けて、実際の長さの「半分」で描く!
- 特に、奥行きの長さはマス目の斜め方向の数え方ではなく、横方向の長さの半分で考えること!
この点をしっかり押さえておけば、キャビネット図は怖くありません!最初は少し戸惑うかもしれませんが、何度か練習すれば必ず描けるようになりますよ。
君ならできます。頑張って!
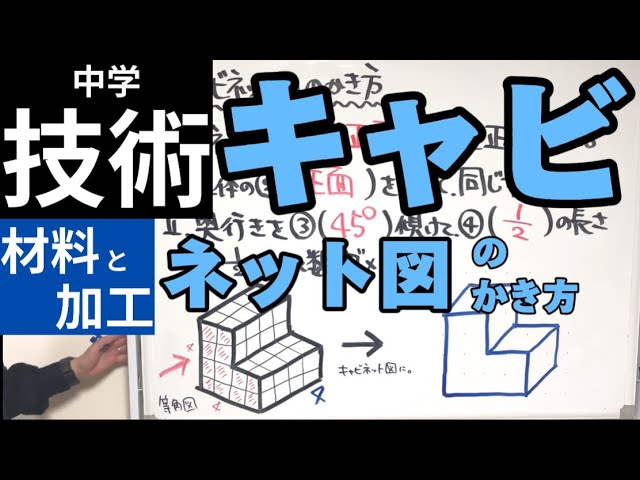

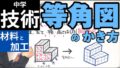

コメント