はい、どうもこんにちは!おきぺんです。
今日は、モノづくりに欠かせない「削る」技術、つまり「切削」について、一緒に深く掘り下げていきます!前回は木材を削る「かんな」について学びましたが、今回はそれ以外のいろいろな工具や、その使い方についてじっくり見ていきましょう。動画の内容をしっかり復習して、実際に作業する時に役立ててほしいです!
削るってどういうこと?「切削」の全体像
「切削」というのは、材料を削り取って形を整えたり、表面を滑らかにしたりする技術のことです。木材、金属、プラスチックなど、いろいろな材料に使うことができるんですよ。今回は、特に中学生のみんなが授業で使う機会が多い工具を中心に紹介していきますね。
身近な工具「ヤスリ」を使いこなそう
まず最初に紹介するのは、みんなもよく目にする「ヤスリ」です。ギザギザした金属の部分で材料を削り、木でできた柄の部分を持って使います。ヤスリには、削る面の目の粗さ(細かさ)が違う、色々な種類があるんですよ。教科書で「荒目」とか「細目」とか、「単目」や「複目」なんて言葉が出てくるので、確認してみてください。
ヤスリの削り方「直進法」と「斜進法」
ヤスリを使った削り方には、大きく分けて2種類あります。目的によって使い分けが大事ですよ!
- 直進法(ちょくしんほう):狭い面をキレイに削りたい時に使う方法です。ヤスリを材料に対してまっすぐ、前後に動かして削ります。ヤスリの幅くらいの、ピンポイントでキレイに仕上げたい時に向いていますよ。
- 斜進法(しゃしんほう):広い面を、均等に、ざっくりと削りたい時に使う方法です。ヤスリを材料に対して斜めに動かして削ります。直進法よりも一度に広く削れるので、大まかに形を整えたい時や、削る量を多くしたい時に便利です。ただ、直進法よりは仕上がりの「キレイさ」は少し劣ります。
まずは斜進法で大まかに削って、それから直進法で仕上げる、なんていう使い分けがおすすめです!
裏技!?「ドレッサ」ってどんな工具?
次に紹介するのは「ドレッサ」です。これは、いわば「替え刃式ヤスリ」のような工具で、ヤスリの金属部分が交換できるようになっています。見た目はヤスリの金属版やプラスチック版といった感じで、赤い色をしていることが多いですね。
ドレッサは主に「小口削り(こぐちけずり)」、つまり材料の端っこ(断面)を削るのに使われますが、もちろん表面を削ったり、角を整えたりするのにも使えます。最大のメリットは、刃を交換できること!粗い刃と細かい刃を付け替えることができるので、これ一本で色々な削り方ができるのが便利です。
ヤスリやドレッサを使った後は、削りカスが刃の目詰まりを起こすことがあります。詰まった削りカスは、ワイヤーブラシやハケを使ってキレイに取り除いてくださいね。絶対に「フーッ」と息で吹き飛ばさないでください!細かい金属片などが目に入ったら大変危険ですよ。
作業効率アップ!「ベルトサンダー」の使い方と注意点
最後に紹介するのは、学校でもよく使う機会があるかもしれない「ベルトサンダー」です。これは、削るための電動工具です。金属加工で紹介した「糸のこ盤」の、削るバージョンだと考えてもらうとイメージしやすいかもしれませんね。
ベルトサンダーは、帯状(ベルト状)のヤスリがセットされていて、スイッチを入れるとそれが高速で一方向にぐるぐると回転します。そこに板材などを押し付けると、自動でどんどん削れていく、とても便利な機械です。
ベルトサンダーを使う時の最重要ポイント「安全第一」!
ベルトサンダーはとても便利ですが、その分、使い方を間違えると大きな事故につながる可能性がある、非常に危険な工具でもあります。以下の点には特に注意して、必ず守ってくださいね。
- 材料の固定:材料を強く押し付けすぎると、材料やベルトが弾け飛んでしまうことがあります。しっかり固定し、無理な力を加えないようにしましょう。
- 身だしなみ:髪の長い人は、必ずしっかり結んでください。袖が長い服やだらしない格好も危険です。高速で回転する部分に巻き込まれたら大変な事故になりますよ。
- 保護具の着用:必ず保護メガネを着用してください! 削りカスが目に入るのを防ぐためです。
- 削りカスの処理:削りカスは適切に処理しましょう。
電動工具は作業が楽になる便利な道具ですが、その便利さの裏には常に危険が潜んでいます。授業で先生から注意されることは、絶対に守るようにしてくださいね。みんなの安全が最優先です。
まとめ
今回は、「切削」という技術について、ヤスリやドレッサといった手工具から、ベルトサンダーのような電動工具まで、色々な道具とその使い方、そして何よりも大切な「安全」について学びました。
材料をきれいに削るには、道具の特性を理解し、適切な使い方をすることがとても重要です。特に電動工具を使う際は、常に危険と隣り合わせだという意識を持って、真剣に安全に配慮しながら作業に取り組んでください。
君ならできます。頑張って!
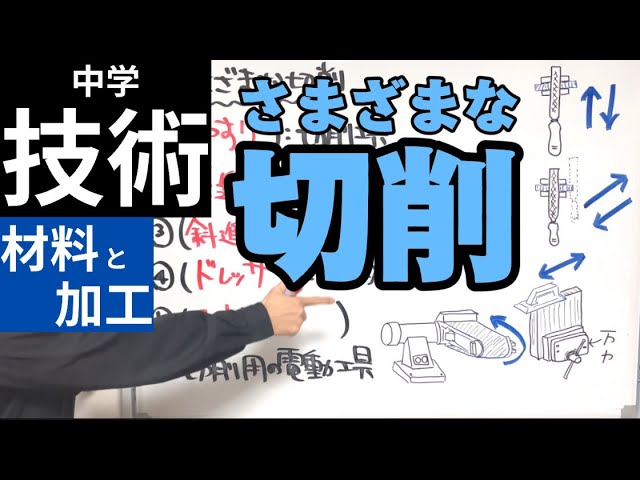



コメント