みんな、こんにちは!元中学校技術科教員のおきぺんです。
いつも「ギリギリ技術」の動画を見てくれてありがとうございます!
前回までは電気回路やエネルギー変換の話をしてきましたが、今回はちょっとドキッとするお話です。そう、電気って実は危ないものなんですよね。でも安心して!僕たちの生活に欠かせない電気を安全に使うための技術が、ちゃんと組み込まれているんですよ。
今日は、電気にまつわる事故と、それを防ぐスゴい仕組み「ブレーカー」について、一緒に楽しく学んでいきましょう!
電気事故から身を守る!知っておきたい2つの現象
まずは、電気で起こりうる危険な現象を2つご紹介しますね。
1. 漏電(ろうでん)って何?
「漏電」とは、電気が本来流れるべき場所(回路)から外に漏れ出してしまうことを言います。
- 例えば、濡れた家電に触れた時。
- ホコリや湿気(しっけ)が原因で、電気が意図しないところに流れてしまうこともあります。
漏電すると、そこから火事(かじ)が起きたり、感電につながったりする危険があるんですよ。
2. 感電(かん でん)ってどんな時?
「感電」は、その名の通り、人の体に電気が流れてしまうことです。
- 漏電した家電に触れて、体がビリッとするケース。
- 自然現象の雷(かみなり)が体に落ちるのも感電の一種ですね。
どちらも、僕たちの生活を危険にさらす可能性があるので、しっかり理解しておくことが大切です。
電気事故から僕たちを守るヒーロー!「ブレーカー」の秘密
そんな漏電や感電を未然に防いでくれるのが「ブレーカー」です!
ブレーカーは、異常な電気の流れを感知すると、自動的に電気の供給をシャットダウン(遮断)してくれる頼れる安全装置なんです。
みんなの家にも、玄関や台所の近くに「分電盤(ぶんでんばん)」として設置されていますよ。ぜひ探してみてくださいね。
ブレーカーは3種類!それぞれの役割を見てみよう!
実は、分電盤の中には大きく分けて3つのブレーカーがあるんですよ。それぞれ大切な役割を担っています!
1. 電流制限器(でんりゅうせいげんき):電気の使いすぎを防ぐメインスイッチ!
これは、一番大きなオンオフのスイッチで、「④」と動画では紹介していますね。
電力会社と契約した電気の量(電流)を超えて電気を使った時に、家全体の電気を自動で「オフ」にしてくれる機能です。
2. 漏電遮断器(ろうでんしゃだんき):感電から命を守る一番大事なブレーカー!
次に「⑤」として紹介されるのが、僕が特に安全面で重要だと考えている「漏電遮断器」です。
これは、洗濯機などの家電で漏電を感知すると、すぐに電気を遮断し、感電事故を未然に防いでくれる、命を守るための大切なブレーカーなんです。
3. 配線用遮断器(はいせんようしゃだんき):部屋ごとの使いすぎを防ぐ賢い番人!
そして「⑥」は「配線用遮断器」です。
これは、台所、お風呂、リビングなど、家の中の場所ごと(回路ごと)に設置されています。
例えば、冬にホットプレートやストーブ、オーブンなどを一つの回路で使いすぎて、許容量を超えると、その回路だけを「オフ」にしてくれます。急に電気が落ちた経験、ありませんか?それはこのブレーカーが働いた証拠なんですよ。
今日のまとめ!電気の安全、バッチリ理解できましたか?
今日は、僕たちの生活に欠かせない電気を安全に使うための大切な知識を学びましたね。
漏電と感電という電気の危険な現象、そしてそれらから私たちを守ってくれる3つのブレーカー
(電流制限器、漏電遮断器、配線用遮断器)の役割について、しっかり理解できたでしょうか?
教科書には、今日の学習内容の図や詳しい解説が載っているはずです。ぜひもう一度見直して、理解をさらに深めてみてくださいね!
君ならできます。頑張って!
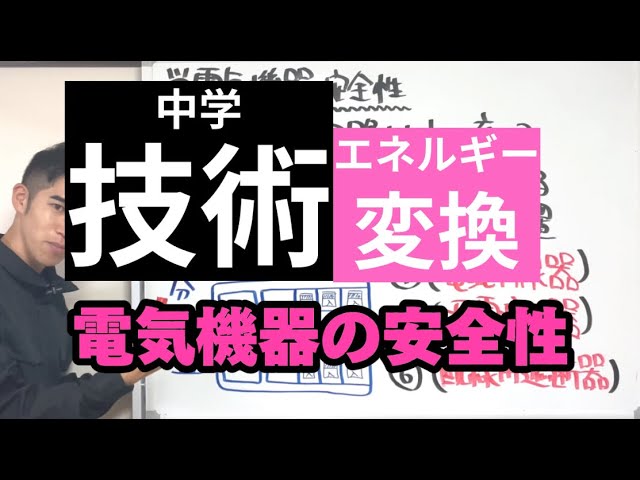


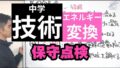
コメント