こんにちは、おきぺんです!
みんなの身の回りにある家電やスマホがどう動いているのか、その「考え方」を学ぶための大切なツール、「フローチャート」について、今回は一緒に見ていきましょうね!
プログラミングの「考え方」を可視化!フローチャートとは?
コンピューターは「プログラミング言語」で書かれた指示で動きます。でも、コードを書く前に「どのように処理が進むのか」という「プログラミング的思考」を理解することが非常に重要なんです。その思考を図で表したのが、このフローチャートです。今回は、フローチャートで使う3つの基本的な処理について、元中学校技術科教員のおきぺんが、みんなにわかりやすく解説していきます。
フローチャートの基本!3つの処理を覚えよう
1. 上から順番に進む「順次処理」
一番基本となるのが「順次処理(じゅんじしょり)」です。これは「上から下に、一つずつ順番に処理を進めていく」という考え方です。
- 始まりと終わりは、丸い形の記号で表します。
- 一つ一つの具体的な処理は、四角い形の記号で表します。
例えば、ライトを2回「つけて消す」動作をフローチャートで表す場合、「スタート」→「ライトがつく」→「消える」→「つく」→「消える」→「終わり」のように、四角い処理が順番に並んで進むイメージです。
2. 同じことを繰り返す「反復処理」
次に、「反復処理(はんぷくしょり)」です。これは「同じ作業を繰り返し行う」ときに使う処理のことです。
もしライトを5回点滅させるとしたら、順次処理では「つく→消える」を5回も書くことになり、フローチャートがとても長くなってしまいます。そこで、反復処理のブロックが役立ちます。
- 繰り返したい処理を、特別な「繰り返し」ブロックで囲みます。
- そのブロックの中には、1セット分の処理だけを書けばOKです。
例えば、ライトを5回点滅させる場合、フローチャートでは「繰り返し5回」というブロックの中に「ライトがつく」→「ライトが消える」という1セットの処理を書きます。これにより、たったこれだけでライトが5回点滅してくれるわけです。
3. 条件によって動きを変える「分岐処理」
そして3つ目は、「分岐処理(ぶんきしょり)」です。これは「ある条件によって、その後の処理を分けていく」考え方です。
- 条件が満たされるか否かで、フローチャートの進む道が2つに分かれます。
- 「はい(Yes)」の場合と、「いいえ(No)」の場合で、別の処理に進みます。
例えば、ライトに「1m以内に人がいるか?」というセンサーが付いている場合、フローチャートではひし形のような図で「人がいる?」と問いかけます。「はい」なら「ライトをつける」、「いいえ」なら「ライトをつけない」というように、条件で動きを変えるんですね。
3つの処理を組み合わせると、身近なシステムも作れる!
今回学んだ順次処理、反復処理、分岐処理の3つは、単独だけでなく組み合わせて使うこともできるんですよ!
例えば、「1m以内に人がいる」という条件が「はい」だった場合に、「ライトを5回点滅させる」反復処理を入れると、「人が近づいたらライトが5回点滅する」という、より高度な動きが作れますね。
みんなのスマートフォンのアプリも、実はこの考え方で動いています。「ここをタップされたらアプリが起動する」のは分岐処理ですし、アプリを長押ししてブルブル震えながら移動するのも、反復処理の一種かもしれませんね。
まとめ:プログラミング的思考を身につけよう!
今回は、プログラミングの基本的な考え方であるフローチャートと、その中の「順次処理」「反復処理」「分岐処理」の3つの種類を学びました。
- 順次処理:上から順に処理を進める。
- 反復処理:同じ作業を繰り返す。
- 分岐処理:条件で処理を分ける。
これらの考え方を理解しておけば、技術科の授業でブロックを組み合わせてアプリやゲームを作る時に役立ちますし、テスト対策にもなりますよ!
君ならできます。頑張って!
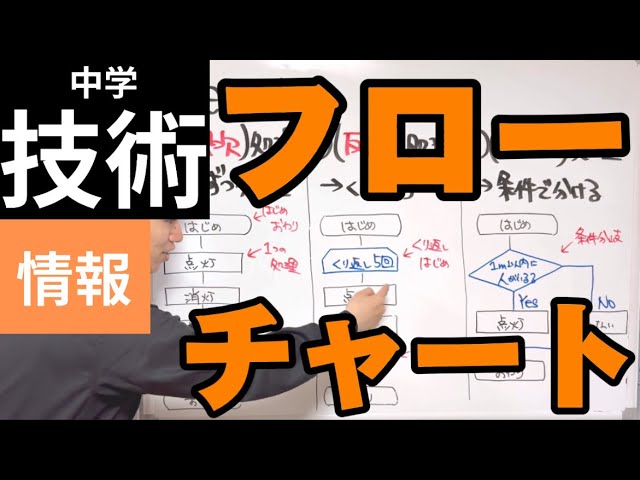


コメント