こんにちは!おきぺんです。
前回の「けがき」で印をつける練習、バッチリでしたか?今回はその次のステップ、いよいよ木材を「切断」する作業に入ります!木材を切るための大切な道具、両刃のこぎりについて、僕と一緒にじっくり学んでいきましょう!こののこぎりの秘密を知れば、もっと上手に使えるようになりますよ!
両刃のこぎりの「各部分」の名前を知ろう!
まずは、両刃のこぎりのそれぞれの部分にどんな名前がついているのかを覚えましょう。知っていると、もっとのこぎりが身近に感じられるはずです。
各部の名称
- 鋸身(のこみ):のこぎりの金属の部分全体を指します。
- 刃渡り(はわたり):鋸身の中でも、刃がついている部分のことです。
- 柄(え):のこぎりの持ち手の部分ですね。
- 柄頭(えがしら)・柄尻(えじり):柄の中でも、さらに細かい部分の名称です。
これらの名前は、技術のテストにもよく出ることがあるので、しっかり覚えておいてくださいね。
2種類の「刃」の使い分けがポイント!
両刃のこぎりという名前の通り、こののこぎりには2種類の刃がついています。これがとっても重要なんです!木材の切り方によって使い分けるんですよ。
縦挽き用の刃(たてびきようのは)
まず一つ目は、縦引き用の刃です。これは、のこぎりの2つの刃のうち、歯が大きい方になります。
- 形の特徴:まるでノミのような形をしています。
- 使い方:木材の繊維の方向に沿って切る時に使います。
- イメージ:木材の繊維は細長い棒が束になっているイメージです。この刃は、その繊維をノミで「かき分ける」ように、奥へ奥へと掘り進むような働きをします。
- 難易度:縦引きは結構力が必要になることが多いので、実際に使うと「うわ、大変!」って感じるかもしれませんね。
横挽き用の刃(よこびきようのは)
そして二つ目は、横引き用の刃です。こちらは、歯が細かい方の刃になります。
- 形の特徴:小刀(こがたな)のような形をしています。
- 使い方:木材の繊維の方向に対して垂直、または斜めに切る時に使います。
- イメージ:小刀で「断ち切る」ように、繊維をスパッと切っていくイメージです。
- 難易度:僕の経験上、縦引きに比べて、横引き用の刃の方が比較的スムーズに、少ない力で切ることができますよ。
どちらの刃を使うかは、切る方向と木材の繊維方向の関係で決まるので、ここが両刃のこぎりを使いこなす上での一番のポイントです。しっかり区別して使い分けられるようになりましょう!
「アサリ」って何?のこぎりを使いやすくする秘密!
さて、のこぎりにはもう一つ、知っておくべき大切な秘密があります。それが「アサリ」という構造です。
アサリとは?
アサリ(あさり)とは、のこぎりの刃(鋸身)が、左右に交互に少しずつ振り分けられている構造のことです。動画の図を見ると分かりやすいのですが、のこぎりを縦(奥から手前)に見た時に、刃が右、左、右、左とギザギザに開いているのがわかるでしょうか?
なぜアサリが必要なの?
このアサリがある理由は、ズバリ、摩擦(まさつ)を小さくするためなんです!
- のこぎりの刃が左右に開いているおかげで、のこぎりが木材の中を進むときにできる「溝(みぞ)」の幅(これを引き溝の幅、またはアサリ幅とも言います)が、のこぎり自体の厚みよりも広くなります。
- この溝と刃の間にできるわずかな「空間」が、木材と刃がこすれる摩擦をグッと減らしてくれるんです。
- 摩擦が小さいと、のこぎりは少ない力でもサクサクと木材を切ることができます。もしアサリがなかったら、のこぎりは木材に強く挟まれてしまって、すごく力が必要で、全然引けないなんてことになっちゃうんです!
だから、私たちが普段使っているのこぎりが「あれ?意外と簡単に切れるな」と感じるのは、このアサリのおかげなんですよ。のこぎりの賢い工夫が隠されているんですね!
まとめ
今回は、両刃のこぎりの各部分の名前、木材の繊維方向に応じた縦引き用と横引き用の2種類の刃の使い分け、そしてのこぎりをスムーズに切るための秘密「アサリ」の仕組みについて学びましたね。
今回覚えた新しい言葉やポイント、しっかり頭に入れておいてくださいね!次回は、この両刃のこぎりを使って、実際にどうやって切っていくのかを学びます。きっともっとのこぎりが得意になりますよ!
君ならできます。頑張って!
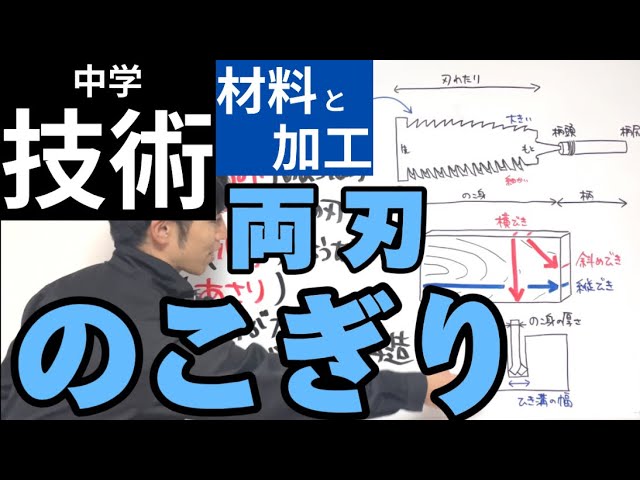



コメント